
獅子道ファングッズなら、https://shishido.official.ec/
獅子道ファングッズなら、https://shishido.official.ec/
[公式LINE]からお申し込み
株式会社獅子道 新宿津軽三味線教室・出張演奏は日本文化なびへ


津軽三味線Wiki
2. 歴史
幕末〜昭和を生きた津軽三味線の祖 仁太坊(にたぼう、Nitaboh)
邦楽史上、津軽三味線の始祖とされる伝説の三味線弾きといえば仁太坊である。 本名を秋元仁太郎(あきもと・にたろう)という。 「坊」とは坊様(ぼさま)の坊。津軽地方では門付け(かどづけ)をする男性の盲人のことを坊様といった。門付けとは人家の門前や庭に立って音曲を演奏し、祝儀を受け取る大道芸能の一種である。元来は季節によって神が家々を訪れ祝言を述べたという民俗信仰に由来する。仁太郎もまた坊様として活動するようになり「仁太坊」と呼ばれることとなった。 1857年(安政4年)に金木新田(かなぎしんでん)の神原(かんばら)村(現在の青森県五所川原市金木町神原)に生まれた仁太郎は、8歳で天然痘にかかる。感染力と致死率の高さから人々に恐れられていた天然痘は、江戸時代には子供がかかりやすい小児病として繰り返し流行した感染症だ。高熱が続いた末に命を落とす例が多く、治癒しても顔や手足に発疹の痕が残る。仁太郎は奇跡的に一命を取りとめたが、失明してしまう。 当時の幕藩体制下では目の不自由な少年が経済的に身を立てるために琵琶や三味線、そして按摩や鍼灸の技能を習得する職能ギルドのような組織が存在していた。これを当道座(とうどうざ)という。最高位を検校(けんぎょう)とし、その下に別当、勾当(こうとう)、座頭などの位階が続くピラミッド型の組織で、形式的には寺社奉行が取り仕切っていたが、会計など事務的な作業も盲人が自ら行う互助的な性格の強い組織体として運営されていた。 所属できるのは盲目の男性のみ。盲目の女性向けには瞽女座(ごぜざ)と呼ばれる同様の組織が存在していた。 門付けや按摩の縄張りを当道座に独占されることによって、盲人の職業的な保護を幕府公認で行ったわけである。当道座での修業を経ることで、門付けをして米や金銭を受け取ることが許される。 しかし、当道座もまた封建体制の中の身分制組織であり、渡し守の子である仁太郎は当道座に入ることが許されなかった。渡し守のような「筋目悪しき者」の子は、当道座では弟子に取らないこととされていたのである。 そうしていながらも、失明後の仁太郎は周囲の村人らが驚くほどの聴覚能力の異様な発達を見せていた。そんなある日のこと、神原村を流し歩いていた瞽女(ごぜ、盲目の女性旅芸人)が奏でる三味線の音色を耳にした。このことが仁太郎の逆境の少年期の一大転機となるのだった。 瞽女が奏でる三味線の音色に激しく心を動かされた仁太郎はこの頃10歳。父・三太郎が瞽女に願い出て仁太郎に三味線を習わせると、たちまち才能の片鱗を見せ始め、異様な習得能力でたちまちさまざまな曲を覚えていった。この時から仁太郎は三味線弾きとして生きていくことを決意しているのだが、そのしばらく後、再び仁太郎に逆境が襲いかかる。父・三太郎の急死である。 三太郎は岩木川の河原の舟小屋に住み渡し守を務めていたが、ある日、悪天候で増水した岩木川で流されあっけなく水死してしまう。なお、仁太郎の母は出産後しばらくして体を壊して亡くなっている。 父・三太郎が亡くなったこの年は慶応2年(1866年)のことだった。こうして天涯孤独の身となった仁太郎は、いよいよ三味線一本で生計を立てていかなければならない窮地に追い込まれてゆく。 だが、時代は幕末から明治に向かう歴史の激動期である。 明治維新後の1871年(明治4年)の太政官布告「盲人之官職自今以後被廃候事」の布告によって、当道座が廃止・解体されたのだった。 当道座の解体は、それまで幕府の管轄下で座頭たちが独占していた芸能の開放を意味する。身分制の廃止によって誰がやってもよいことになったのである。「筋目悪しき者」とされ当道座に入れなかった仁太郎も自由に芸をすることができるようになる。 明治維新が千載一遇のチャンスをもたらし、芸の開花につながる。ここに後の津軽三味線の発生にいたる歴史的転換点があった。 ここからが三味線弾きとしての仁太郎の快進撃の始まりである。 明治維新後の芸能の開放によって自由に芸ができる環境を得た仁太郎だが、門付けを生業とする坊様「仁太坊」として公に活動を始めるにあたって、もうひとつ重要な意味を持つ制度改革が行われていた。 明治4年(1871年)の虚無僧(こむそう)制度の廃止による尺八の開放だ。 虚無僧とは普化宗(ふけしゅう)の修行僧のことを言う。普化宗は「尺八を吹くこと」を悟りへ道とする禅宗の一派で、武家出身でなければ入門が許されなかった。尺八という楽器は、明治維新以前の虚無僧が独占する法器として扱われ、一般人には触れることが許されない楽器だったのである。 だが、仁太郎は少年時代に失明した後、舟場を偶然訪れた虚無僧から尺八の簡単な手ほどきを受けており、仁太郎にとって尺八は少年時代からの憧れの楽器だった。 虚無僧制度の廃止以降、尺八は誰もが扱える楽器として開放された。仁太坊もまた誰に断ることもなく自由に門付けで尺八を吹くことができるようになった。ここから青年期の仁太坊の芸人人生が始まる。 坊様としての仁太坊は、背中に三味線を背負い、腰に尺八と竹笛を差す独特の格好で各地域のお祭りに姿を現し、評判を呼ぶ。 笑いを意図した漫芸である「謎かけ」も得意とした。客からお題をもらって「○○とかけまして○○とときます。そのこころは」と言葉遊びでうまいことを言う。謎かけは現代でも寄席芸として行われている。 さらに仁太坊が注目を集めたのは一人で八人分の芸をする「八人芸」だった。三味線、尺八、太鼓、声色など八人分の芸を一人で同時に行う大道芸の一種だが、明治維新以前は座頭が見世物小屋や寄席で行っていたため「八人座頭」と言われていた。 こうして着実に評判を得ながらも、仁太坊の芸のあくなき探究は続く。 弘前の芝居小屋「茂森座」で義太夫節を聴き、その音色に惚れ込んだ仁太坊が太棹三味線を初めて手にしたのは明治11年(1878年)のことだ。そして太棹を手にした仁太坊は、弦を激しく打ちつけダイナミックな低音の魅力を発揮する独自の奏法「叩き奏法」を編み出してゆく。その後、15歳の少年の古川喜之助(こがわ・きのすけ)を一番弟子とし、生活を共にする内弟子として迎え入れたのは明治13年のことだった。 喜之助を弟子に取った明治13年だが、この2年ほど前に妻のマンと結婚した仁太坊に第1子の作助が生まれたのは明治13年11月のことだった。 内弟子となった喜之助は仁太坊夫婦と一つ屋根の下で生活を共にし、三味線修業を始める。封建時代の芸風を踏襲することを良しとしなかった仁太坊の姿勢は、弟子の教育においても一貫していた。「人まねだったら猿でもできる。おまえはおまえの三味線を弾け!」との思想である。そして明治14年の晩秋の頃、喜之助は坊様として独立し、喜之坊として故郷の南津軽荒田に帰ってゆく。 仁太坊のもとに2人目の弟子志願者が現れたのは明治21年のことだ。長泥村(ながどろむら)から訪ねてきた太田長作(おおた・ちょうさく)である。長作は幼年期に失明。15歳で三味線弾きになることを決意する。仁太坊の通いの弟子となった長作は、杖を頼りにして長泥から神原まで歩いて通った。3年の修業の後に独立した長作坊は明治28年に長泥から狐森(きつねもり)に移り住むが、門下に300人の弟子を抱えるまでになった。後に名人と言われる梅田豊月(うめだ・ほうげつ)もまた長作坊の門弟の一人である。 時代は近代化の巨大な開発のうねりの渦中にあった。津軽の近代化の象徴として、蒸気機関車が初めて到達したのは東北本線の上野-青森間が全線開通した明治24年のことだ。そして日清戦争(明治27〜28年)日露戦争(明治37〜38年)の経て世界は帝国主義全盛期に入ってゆく。こうした激動の時代のなか、仁太坊の最後の弟子となる白川軍八郎(しらかわ・ぐんぱちろう)少年が弟子入り志願に訪れたのは、大正6年(1917年)のことであった。 【参考文献】 ・松木宏泰『津軽三味線まんだら 津軽から世界へ』(邦楽ジャーナル、2011年刊) ・大條和雄『津軽三味線の誕生 民俗芸能の生成と隆盛』(新曜社、1995年刊) ・『新撰 芸能人物事典 明治~平成』(日外アソシエーツ、2010年刊) ・MichaeSl . Peluse「Not Your Grandfather's Music: Tsugaru Shamisen Blurs the Lines between "Folk,""Traditional," and "Pop"」( 『Asian Music』誌36号所収、テキサス大学出版部、2005年刊) ・GERALD T. McGOLDRICK「TSUGARU SHAMISEN AND MODERN JAPANESE IDENTITY」(カナダ・ヨーク大学大学院哲学科博士論文、2017年)
幕末〜昭和を生きた津軽三味線の祖 白川軍八郎(しらかわぐんぱちろう、Gunpachiro Shirakawa)
白川軍八郎(1) 大正6年(1917年)、この年還暦を迎えた仁太坊に9歳で弟子入りした白川軍八郎はめきめきと三味線の腕を上げ、14歳になる頃には仁太坊の奏法のほぼすべてを習得し、数百年に一度現れるかどうかの天才だとすら言われた。仁太坊から独立した後も、のちの津軽三味線の標準的技法となるような洗練された奏法を独力で練り上げ完成させてゆく。ところで、仁太坊の弟子の中でもSP盤音源が残されているのは、白川軍八郎だけである。テイチク、リーガル、ビクターなど複数レーベルの音源が存在しているが、白川軍八郎が生きた時代は蓄音機の世界的な普及期にあたり、家にいながらにして音楽を聴く体験を人類が初めて経験した時期だということになる。日本における蓄音機の歴史は、明治20年代にさかのぼる。蝋を塗った細長いシリンダーの表面に音を記録する「蝋管式」と呼ばれる蓄音機が日本に持ち込まれたのは明治23年のことだった。 「蓄音機がわが国へ渡来したのは、明治二十三年(一八九〇)頃で、始めは浅草の花屋敷で、蝋管からの発声をゴム管で耳にあてて聞かせる仕方で、余興としてお目見栄したとされている。」(松本重雄「大正時代の銀座の系譜」『貯蓄時報』1978年6月号)われわれが知る円盤型のレコード盤が登場するのは蝋管式のしばらく後だが、日本初の蓄音機吹き込みが行われたのは、英国のレコード会社グラモフォンの録音技師フレッド・ガイスバーグが日本を訪れた明治36年(1903年)である。築地のメトロポールホテルに落語家や浪曲師が招集され、その一室で吹き込みが行われた。その後、米国のコロンビアやビクターをはじめ欧米レコード会社が相次いで日本市場に参入してくる。当時の欧米レコード会社は蓄音機の市場開拓のため、世界中で大がかりな出張録音を敢行していた。渡航先で録音した原盤を持ち帰り、自国工場でプレスしたレコード盤を録音元の国・地域へ蓄音機とともに輸出する。蓄音機のハードと現地化したソフトを同時に輸出するビジネスモデルで、世界に蓄音機の市場を急速に拡大させていった。 日本における蓄音機製造とレコードプレスの国産化は、日米蓄音機製造、のちの日本コロムビアが設立された明治40年(1907年)以降のことである。日本コロムビアのレーベルとしては「ニッポノホン」がよく知られているが、白川軍八郎の盤もある「リーガル」は昭和8年以降にリリースされた大衆向けレーベルであった。 白川軍八郎(2) 白川軍八郎は16歳の時に小原家万次郎一座に入る。大正13年のことである。だが、大正15年には万次郎が一座を妹の三上鶴子に譲ったことにより、軍八郎もまた三上鶴子一座の所属となった。一方、昭和3年には津軽で天才民謡歌手といわれた工藤美栄を座長とする陸奥乃家(むつのや)演芸団が旗揚げしている。そこに軍八郎は昭和10年に入団することになる。 軍八郎の弟子の秋元博が2013年に『秋田魁新報』の取材に答えた「シリーズ時代を語る」の記事によると、秋元博が弟子入りした当時、その曲弾きですでに名人と言われていた軍八郎は39歳だった。 陸奥乃家演芸団は、中津軽郡千年村(ちとせむら)小栗山(こぐりやま)の工藤美栄の自宅を拠点とした一座で、軍八郎はその家の2階の一室をあてがわれていたのだという。 だが、座員が家で寝起きするのは年に1カ月程度、ほとんどの期間は巡業に出ていた。まず大みそかに弘前を出発し、元日から北海道の函館で正月興行が1週間、そして1月中は北海道内の炭鉱や漁港を回る。桜の季節になれば弘前に戻って観桜会の舞台をこなし、そして東北各地を巡業する。巡業の合間に弘前に戻っても工藤家のリンゴ畑の収穫や運搬の手伝いに座員たちが駆り出されていた。 秋元と同時期に陸奥乃家演芸団に所属していた軍八郎の弟子に、金谷美智也がいた。それが後の三橋美智也である。 美智也は昭和5年(1930年)、北海道上磯町生まれ。母親の金谷サツが民謡歌手だったこともあり、5歳から民謡を歌い、天才民謡少年と呼ばれるほどの才能を示していた。16歳で陸奥乃家演芸団に入団し、軍八郎の弟子として三味線の修業に明け暮れる。 そんな美智也が陸奥乃家演芸団を離れて上京するのは19歳の時だ。陸奥乃家演芸団の巡業先の秋田の横手でたまたま入った映画館で見た東京のシーンが上京のきっかけとなったのだという。 【参考文献】 「シリーズ時代を語る:[秋元博]弘前の演芸団に入る」(『秋田魁新報』2013年8⽉22⽇付) 「シリーズ時代を語る:[秋元博]師匠は「うん」の一言」(『秋田魁新報』2013年8⽉23⽇付) 「シリーズ時代を語る:[秋元博]津軽では皆が作曲者」(『秋田魁新報』2013年8月25日付) 「シリーズ時代を語る:[秋元博]みっちゃんの思い出」(『秋田魁新報』2013年8月27日付) 「シリーズ時代を語る:[秋元博]美智也の確かな功績」(『秋田魁新報』2013年8月28日付)
幕末〜昭和を生きた津軽三味線の祖 三橋美智也(みはしみちや、Mihashi Michiya)
三橋美智也(1) 三橋美智也が民謡歌手として初めてレコードの吹き込みをしたのは小学校6年生になる12歳の頃だった。8歳で全国民謡コンクールで優勝し、すでに民謡界の神童といわれるほどに名を馳せていた美智也にコロムビア・レコードから声がかかる。1942年(昭和17年)3月のことだった。日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告したのはその前年の1941年(昭和16年)。戦時の暗い世相が覆うなか、美智也はあこがれの東京に向かうことになる。コロムビアの東京本社で「江差追分」など数曲を吹き込んだが、このレコーディングには北海道きっての三味線の名手とされた鎌田蓮道が尺八と三味線で参加している。それほどにコロムビアからの期待は強かった。翌年、函館市内の高等小学校(現在の中学校に相当)に進学した美智也は、コロムビアのレコード吹き込みの縁から鎌田蓮道の弟子となり三味線の手ほどきを受けるようになる。だが、太平洋戦争の戦況悪化に伴い、物資不足と食糧難はひどくなる一方だった。美智也は貧しい家計を支えるため、三味線を手ににわか作りの舞台で民謡を唄い、お米をもらい受けて帰る日々であった。昭和19年ごろには戦況はますます悪化し、ついに勤労動員に駆り出されることになる。学校のクラスの先生の引率でパルプ工場や造船所、ドラム缶製造所などに引き連れられてゆくが、先生のいいつけで慰安として工場の隅に舞台を作り民謡を唄うのが美智也の役割でもあった。こうして勤労動員に従事しながら高等小学校を卒業した5カ月後の1945年(昭和20年)8月、日本は終戦を迎えることになる。後年、美智也は自伝で以下のように回顧している。「思えば昭和十六年十二月八日の第二次世界大戦の勃発から二十年八月十五日の敗戦までの足かけ五年という歳月は〝残酷な悪夢〟のような時代でした。戦争という名のもとに、多くの人々が苦しく悲しい体験を余儀なくされたわけです。夫を戦地で失った人たち、飢餓に悩まされ、食物もロクロク食べられず栄養失調になった人、学業もほうり投げて、軍需工場で働かされた青少年......。そんな時代を生きてくると、強靱な精神の持ち主になるようです。(どんなことがあってもくじけないぞ)といった強さが培われるのかもしれません。私の場合もそうでした。」(『ミッチーの人生演歌』) だが、敗戦後の混乱の中でなおも物資不足と食料難は続き、物資不足によるインフレが庶民の生活苦に追い打ちをかける。美智也は民謡を唄い、わずかのお米や野菜をもらい受ける生活であった。敗戦後の物価高騰は1945年の物価水準をベースとすると1949年までの5年間で約70倍にいたるほどの激烈なハイパー・インフレーションであり、日本は「全国飢餓地獄」とすら言われた世相の時代である。美智也はその後、1954年(昭和29年)に「酒の苦さよ」でキングレコードから歌手デビューすることになるが、むろん、その道のりは平坦ではなかった。 三橋美智也(2)
東北地方での巡業生活の日々のなかで日に日に募っていった美智也の思いは、芸人の世界への嫌気だった。 「こういう生活では安定性もない。東京へ出て、大学を卒業して、堅気のサラリーマンになろう。いや、将来は実業家をめざそう」(『ミッチーの人生演歌』) こうして美智也は、巡業一座を脱出して東京に出ることを腹の中で決意するのだが、その翌日の楽屋で偶然、師匠の白川軍八郎と二人きりになった。 「やっぱり東京だよ。東京へ行きなさい。君は東京へ出て民謡を教えて生活ができる。食うには困らないだろう。あるていど生活のメドがついたら上の学校へ行きなさい。これからの日本は学校を出ていないければ一人前のあつかいを受けなくなる」(同) 東京行きの希望について美智也が白川軍八郎に話したことは一度もなかった。にもかかわらず、静かな口調でそう言われたのだという。 そして一座脱出を決行する日が来る。巡業公演が終わった後ひそかに荷造りをし、リュックサックと太ざお三味線を手に夜行列車に乗り込む。超満員の列車のなか一睡もせずにたどりついた上野駅は、焼け野原にバラックが建ちならび復員兵や痩せこけた老人たちがただただ蠢いている混沌とした世界だった。 右も左もわからない状況ですぐに仕事を見つけなければ食っていけない現実を突きつけられた美智也は、当時の人気喜劇俳優だったエノケン(榎本健一)かロッパ(古川緑波)のどちらかに弟子入りしようと思い立つ。まず、浅草のエノケン邸を訪ねる。だがエノケン本人は不在だった。奥さんに弟子入り志願を申し出たが丁寧に断られた。ロッパ邸でも同様のありさまであった。 そこで7年前にレコードの吹き込みをしたコロムビア・レコードを訪ねた。だが、やはり相手にされなかった。 困り果てた美智也の頭にふと浮かんだのが、当時、国民的人気を博していた民謡歌手の菊池淡水(きくち・たんすい)の名前だ。次は菊池淡水が住む鎌倉市山ノ内へ向かう。やはり本人は不在だった。しかし、奥さんが親切に近くの旅館を紹介してくれた。旅館で一泊し、夜明け前の午前3時ごろ再び邸宅に向かった美智也は、旅興行から帰宅する菊池淡水を玄関口で待ち構えていたのである。 三橋美智也(3)
玄関先で待ち構え、ついに菊池淡水に会うことができた美智也は、たいへんな温情を受け、その日からすぐに就職先の世話をしてもらうことになる。 淡水に連れられ、仏壇屋、八百屋、鉄工所の下請けなどを訪ねて何軒か歩いた末、横浜の雪見橋にあった雪見湯に就職が決まった。この銭湯の経営者が無類の民謡好きだった縁である。しばらくするとお客さんにも民謡好きが多いことがわかり、お年寄りに民謡を教え始める。 この頃、美智也は19歳になっていた。 そんなある日、民謡を教えていたおばあさんの一人から「綱島温泉の東京園でまじめな青年をほしがっているから、よかったら紹介するよ」と言われる。 綱島温泉といえば、大正時代初期に源泉が発見され鉄道網が整備される昭和初期に栄えた東急東横線・綱島駅近郊の大規模温泉街である。かつては「東京の奥座敷」とも呼ばれていた。中でも東京園は、民謡を習いに来るお客さんが多い「民謡温泉」であった。美智也は雪見湯の経営者の許可を得て、東京園に住み込みで働くことになった。昼間はボイラーマンとして働き、夜は毎晩大広間で民謡を教える生活である。 この頃、ボイラーマンとしての月給が4000円、加えて月謝300円の民謡の教え子が50人で1万5000円になる。燃える向学心に収入が追いついてきたこの年から美智也は横浜外語(YMCA)に入学し、初級英語を勉強し始める。また、東京園の支配人の北沢とし子の勧めで、小型四輪とオートバイの免許も取った。 そして1952年(昭和27年)の4月、美智也は念願の高校進学を果たす。 明治大学付属中野高校に入学したこの年、美智也はすでに21歳になっていた。 働きながらの夜学ではなく、昼間部の三年制高校に通うことができたのは、事情を話してボイラーマンの仕事を休止し昼は学生として、夜は東京園で民謡を教える生活に切り替えることが許されたためであった。民謡の教え子の月謝のみで、学費と生活費を十分にまかなえるまでになっていたのである。
三橋美智也(4)
美智也がキング・レコードと専属契約を結ぶことになったのは高校進学を果たした翌年の1953年(昭和28年)のこと。東京園で民謡を教えていた美智也の第一の弟子である平野繁松が「NHKのど自慢」で1位を獲得、その喉を見込まれキング・レコードが平野のレコードを出す計画が進んでいた。三味線伴奏で美智也もレコーディングに参加したが、この日の平野の調子があまりに悪くレコーディングは中断、計画自体が白紙となってしまう。この時、ディレクターの掛川尚雄が目を付けたのが美智也の存在だった。その後、掛川からしつこく口説かれ、結果としてキング・レコードと専属契約を結ぶことになる。だが、そもそも歌手になりたくて東京に出てきたわけではない。大学まで進学してサラリーマンとして実直に生きることを人生の目標としていた美智也にとって、歌はアルバイト程度のものでしかなかった。デビュー曲の『酒の苦さよ』は1954年1月に発売されたが、売れ行きが芳しくなく、歌は向いてないと思った美智也は、いっそう勉学のほうに力を入れるようになっていった。 しかし、その翌年に転機が訪れる。高校卒業式の直前の1週間前に発売された「おんな船頭唄」だ。当時、キング・レコードの人気歌手だった照菊(てるぎく)が唄う『逢初ブルース』をA面とするシングル盤レコードのB面曲だが、これが初のヒット曲となる。こうして一躍人気歌手の仲間入りを果たした美智也の勢いは止まらない。翌年1956年には1年間で14曲を発売し、「リンゴ村から」の270万枚、「哀愁列車」の250万枚をはじめ、14曲中5曲がミリオンセラーとなった。「三橋で明けて三橋で暮れる」と言われるほどの爆発的な三橋ブームが日本全国を席巻した。経済白書に「もはや戦後ではない」との文言が登場し、日本が高度成長期に突入してゆく時代。集団就職者を中心に農村から都市へ流入していった人々の望郷の歌として、美智也の歌は心を強くつかんだ。そしてデビューから約30年後の1985年には、レコード売上総数が日本初の1億枚突破の金字塔を打ち立てる。美空ひばりのレコード・CD売上総数が1億枚を突破したのが2019年だということを考えると、恐るべき記録である。 ところで、1983年に書かれた『ミッチーの人生演歌』には、「私はこれからも、歌謡曲と民謡と津軽三味線に生命を賭していくつもりです」と記されている。流行歌手として成功を収めたが、その原点は一貫して民謡と津軽三味線にあるのだと力強く宣言していたわけである。そこが「歌謡界の王者」の王者たる所以である。 (おわり) 【参考文献】 『ミッチーの人生演歌』(三橋美智也、翼書院、1983年) 『三橋美智也——昭和歌謡に見る昭和の世相』(荻野広、アルファベータブックス、2015年) 日銀『金融研究』2012年1月号「戦後ハイパー・インフレと中央銀行」(伊藤正直)https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk31-1-7.pdf 「東京園の復活は?幻の楽園「綱島温泉」の痕跡を追う!(はまれぽ.com、https://hamarepo.com/story.php?page_no=1&story_id=7228) 『ミッチーの人生演歌』(三橋美智也、翼書院、1983年) 『三橋美智也——昭和歌謡に見る昭和の世相』(荻野広、アルファベータブックス、2015年)
幕末〜昭和を生きた津軽三味線の祖 木田林松栄(きだ りんしょうえ、Kida Rinshoe)
木田林松栄(1) 戦後日本が高度成長を遂げた1970年(昭和45年)ごろ、津軽三味線の二大名人として「弾きの竹山、叩きの林松栄」と対比され注目を集めたのが、高橋竹山(たかはし・ちくざん)と木田林松栄(きだ・りんしょうえ)である。 木田林松栄は、1911年は(明治44年)に南津軽郡柏木村に生まれる。本名は田中林次郎。父・田中重太郎と母・田中さしの三男として生まれ、子供の頃から門付けに訪れた仁太坊の孫弟子・亀坊(かめぼ)のあとをついて歩いていたぐらい、三味線に魅かれていた。 尋常高等小学校を卒業し、農学校に進学したものの三味線への強い思いから中退し、17歳で吹田三松栄(ふきた・さんしょうえ)の通い弟子となる。その2年後、19歳で陸奥乃家(むつのや)演芸団に入団することになる。昭和5年のことだ。 林松栄の入団からほどなくして福士政勝(ふくし・まさかつ)が同演芸団に入団、その後の昭和10年には白川軍八郎が入団し、一座内で三羽烏と呼ばれるようになる。 林松栄は白川軍八郎の三味線の音色とその技術に衝撃を受けるが、弟子になったわけではなく、楽屋で三味線を弾いていた軍八郎の音色を隠れて必死で盗み聞きしていたのだという。 1932年(昭和7年)には、陸奥乃家演芸団の座長で民謡歌手の工藤美栄のレコード発売のため、林松栄は三味線伴奏でレコード吹き込みを行なっている。民謡興行の中で自らの三味線奏法を模索するが、時代は戦争の真っ只中である。昭和18年には、林松栄にも召集令状が届く。林松栄の豪快な叩き三味線を大衆が耳するのは戦後のことである。 林松栄は迫力ある音色を追求するため、とりわけ一の糸の太さにこだわった。30号が限度だとされる一の糸に、より太い35号を使うようになる。昭和36年には東京の民謡ブームを背景に、民謡酒場の浅草』七五三」の専属になるが、この頃はついに40号の極太を使うまでになっていたのである。
木田林松栄(2) 昭和37年(1962年)に浅草の民謡酒場「七五三」から池袋の宴会場「白雲閣」に移籍した林松栄は、津軽民謡歌手の浅利みきとのコンビで白雲閣の大看板となってゆく。その後、昭和41年に浅利みきとともに独立する。 高橋竹山との対比でいえば、林松栄は津軽三味線の伴奏に軸をおき、民謡の歌い手との関係を前提に演奏を続けていった。一方の竹山は、シャンソン歌手の淡谷のり子が定期ライブを行っていた渋谷の地下小劇場「ジァンジァン」で定期公演を行うようになる。ジァンジァンは当時の前衛演劇やフォークシンガーら、カウンターカルチャーの拠点でもあった。民謡伴奏ではなく三味線だけを聴かせる竹山の演奏は、それまでの民謡界とは別のまったく新たな客層を発見してゆくことになる。 こうして演奏手法や支持層の違いからライバル関係とみなされてゆく林松栄と竹山だが、お互い仲が悪かったわけではない。両者がメディアを通して決定的にライバルとみなされるようになったきっかけは、昭和49年によみうりテレビ「11PM」の企画で制作された芸術祭参加作品の番組『三味線の詩』だといわれる。この番組内で、両者を別々の場所で収録した「三味線は弾くもの」「三味線は叩くもの」との発言を同一画面で流したためだとされる。メディアの煽りによって対立させられ、それ以降、両者の関係が悪くなったという証言もある(「まんよう文化」誌上での木田林松次・三隅治雄対談)。問題の番組『三味線の詩』は昭和50年にLP盤としてキャニオンレコードから発売されるが、竹山本人の許可なく発売されたため、2週間で販売中止、3カ月後に廃盤となる。 竹山の支持層が民謡に縁のないサブカルチャー志向の若者やインテリに支持されたのは、この時代の音楽文化の変化を見るうえで特徴的な現象だが、林松栄は民謡にこだわり多くの弟子を取った。 林松栄は昭和54年1月1日に67歳で亡くなったが、木田流と竹山流は津軽三味線二大潮流として、今なおその底流にある。 【参考文献】 ・松木宏泰『津軽三味線まんだら 津軽から世界へ』(邦楽ジャーナル、2011年刊) ・ 松木宏泰「北の熱き民族音楽 津軽三味線」『Civil Engineering Consultant』2006年7月号 ・大條和雄『津軽三味線の誕生 民俗芸能の生成と隆盛』(新曜社、1995年刊)
幕末〜昭和を生きた津軽三味線の祖 高橋 竹山(たかはし ちくざん、Takahashi Chikuzan)
高橋竹山(1)
1970年代、木田林松栄のライバルとされた高橋竹山は津軽三味線を現代音楽として聴衆に認識させる契機をつくった一方の巨匠である。 竹山が東京・渋谷の小劇場ジァン・ジァンで定期演奏を開始したのが1973年12月だ。ジァン・ジァンは渋谷の公園通りの山手教会地下に1969年オープン。俳優・中村伸郎がウジェーヌ・イヨネスコの不条理劇『授業』を11年間にわたって毎週金曜に演じで伝説となるほか、吉田拓郎、古井戸、泉谷しげる、荒井由実時代のユーミンら、多くのフォークシンガーらが巣立っていった場所でもある。のちに「サブカルの聖地」といわれる。 竹山は渋谷ジァン・ジァンで1973年以降毎月ライブを行い、民謡になじみのなかった若者たちに澄んだ音色の三味線をしんみりと聴かせていた。 竹山は本名を定蔵(さだぞう)という。明治43年(1910年)に東津軽郡中平内(なかひらない)村に生まる。2歳で麻疹にかかり失明。両親は竹山が15歳のときに近くに住む戸田坊(とだぼ)に弟子入りさせる。戸田坊から三味線を習い、共に門付けに歩く日々を送ったが2年ほどで独立。大正15年(1926年)からひとり旅を始める。竹山の人生にとって三味線と民謡はあくまでも生きてゆくための手段だったが、竹山の音感には並外れたものがあった。昭和6年に民謡歌手の函青くに子の一座に入り、旅巡業の中で出合った浪曲三味線をレコードを聴き独学で習得したのだという。だが、紆余曲折は続き、鍼灸師になるため、昭和19年には34歳で靑森の八戸盲唖学校中等部に入学している。5年後、八戸盲唖学校を卒業し、鍼灸と按摩の免状を取得した竹山はさっそく自宅で開業するが商売はさっぱりうまくいかず。そうこうしている間に津軽民謡界で別格の存在とされていた成田雲竹(なりた・うんちく)から声がかかり熱心に口説かれた結果、再び三味線を手にした竹山は、成田雲竹の弟子となり「竹山」の名をもらう。こうして雲竹とコンビを組み、伴奏者して活動することになるのだった。
高橋竹山(2)
民謡歌手の大家である成田雲竹の弟子となった竹山は、1950年(昭和25年)以降、雲竹の伴奏者として雲竹引退までの14年間にわたり活動を共にし、各地を巡業する。雲竹と竹山の師弟関係は厳しいものだった。雲竹は竹山の独自活動を許さず、1963年にキングレコードから『津軽三味線 高橋竹山』をリリースする際も雲竹はなかなか首を縦に振らなかったのだという。竹山が津軽三味線の独奏による自らの音楽性を遺憾なく発揮し始めるのは、1964年に師弟関係が解消された後のことである。 全国的にその名を知られるようになったのは1971年、青森放送の制作によるドキュメンタリー番組『寒撥(かんばち)』の放送がきっかけだ。同番組はこの年の文化庁芸術祭優秀賞を受賞する。以降、竹山の名前の全国化とともに、音楽ジャンルとしての「津軽三味線」が全国的に認識されるようになってゆく。 また、サブカルの聖地と言われた渋谷ジァンジァンで定期演奏を開始する1973年から、竹山の津軽三味線を現代音楽として捉えた若者たちの間で人気が高まり、竹山ブームが巻き起こる。 この時期から竹山と木田林松栄を「弾きの竹山」対「叩きの林松栄」の対比で両者をライバル視する図式がメディアを通して喧伝されてゆくが、「三味線界のジミヘン」とも言われた竹山の音楽性が既存の邦楽の範疇を大きく越え出るものであったことは間違いないであろう。1986年にはアメリカ合衆国での7都市10公演を敢行し、米紙ニューヨーク・タイムズ掲載の論評で「名匠」との賛辞を受ける。このことが津軽三味線の世界化のさきがけとなった。 2021年6月、新興のレコードレーベルVOLUKUTA(フォルクタ)から「岩木即興曲」の京都・円山公園音楽堂でのライブ音源を米国人ジャス・ベーシストのビル・ラズウェルがリミックスした12インチアナログ盤がリリースされた。 生誕から1世紀を経てもなお、竹山が切り開いた新たな音楽性は、世界の音楽の未知の可能性を示唆しているといえるであろう。

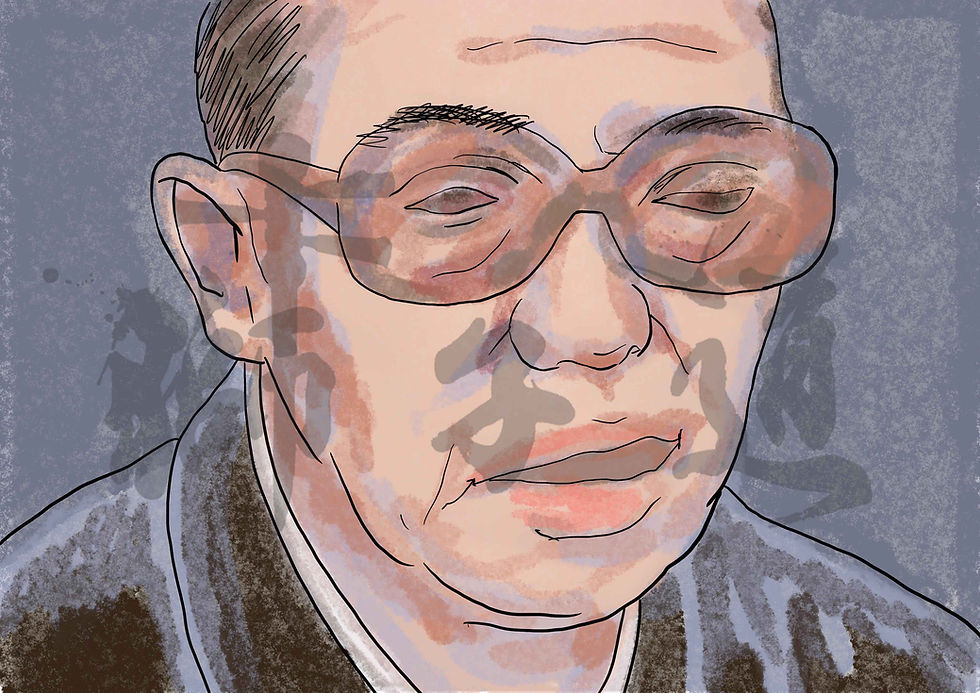

山田千里(1)
山田千里(やまだ・ちさと)は1931年(昭和6年)、豪雪地帯である白神山地の麓、西津軽郡赤石村(現在の鯵ヶ沢町)に生まれる。満州事変の年である。
父の儀助は集落に広大な土地を持つ豪農であった。猟師として働くかたわら、蓄音器で民謡のレコードを聴き、趣味で三味線を弾いていた。子供の頃の千里は、父の三味線を持ちだして遊んでいたという。
戦後になって中学校卒業を翌年に控えた1946年(昭和21年)の春、千里は三味線弾きになりたいと父に打ち明けるが、「遊び人のかまどけしになるなら勘当だ」と叱りとばされ取り合ってもらえない。「かまどけし」とは、かまどの火を消してしまう者、すなわち「破産者」を意味する津軽弁である。儀助は常々、大工か桶屋の弟子になれと千里に言い聞かせていたのだった。
だが、転機はすぐに訪れる。
この年の7月、家から約8キロのところにある千聖が通っていた南金沢小学校に福士政勝(ふくし・まさかつ)一座が巡業にやって来たのである。
父には内緒で8キロの山道を向かった千里は一座の唄会に聴き惚れ、終演後に楽屋付近に寄っていくと、そこにいた一人の男から「一緒に行かないか」と声をかけられる。男が何者なのかはわからなかったが、その男の一言を受け、千里は山道を駆け出しいったん家に戻って父の三味線を持ち出し、すぐに10キロ先にある福士一座の巡業先の明石劇場に向かって三味線を担いで走り出した。
一座は政勝の妻の成田雲竹女(なりた・うんちくじょ)を看板とする7人所帯。この日の夜の公演から千里は幕引きや使い走りなど一座の仕事を手伝い始める。
こうして千里は、家出同然のかっこうで福士政勝の弟子として一座に入団してしまうのだった。
山田千里(2)
福士政勝一座に家出さながらの体で入団した千里は、三味線の稽古を続けるが、次第に三味線それ自体よりむしろ、一座の興行のやり方に関心が向かうようになる。持って生まれた興行師としての勘が目覚めたのか、1949年(昭和24年)には、千里は自らの一座「津軽民謡団」を結成することとなる。団員は千里の最初の妻となる山田百合子を含む7人だった。この年、千里は18歳になったばかり。興行自体が未経験だったにもかかわらず一座は7年にわたって興行を続けることになる。
そうした興行の間にも、千里の妻となった百合子との関係は次第に悪化し、民謡歌手の福士りつを興行に迎えた頃にはすでに関係性は破局に近づいていた。
そして、東京オリンピックが開催された1964年には福士りつと再婚。同年にライブハウス「山唄」を弘前市に開業し、りつと夫婦で経営に携わることになる。
開店にあたって「民謡酒場」の名称をあえて使わず「ライブハウス」と名乗ったのは千里の先見の明と言えるだろう。
興行師としての顔が目立つ千里だったが、三味線奏者としての評価を高めたのは自主制作盤LP『津軽民謡と共に25年/福士りつの唄』を東芝EMIから発売した1974年である。同LPが画家・斎藤真一の目に留まり、以降マスコミで広く取り上げられ、ハンガリーやアメリカなど海外公演のオファーも受けるようになる。
三味線奏者として名手との評価も定まるなか、それでもなお千里の興行師としての魂は燃え続ける。1982年には、日本初の津軽三味線競技コンクールである「津軽三味線全国大会」を自らの手でプロデュースしている。当初は青森放送の25周年記念事業として企画され、予算の都合でいったんお蔵入りになったが、千里のプロデュース能力で現実化させたたわけである。
こうした津軽三味線普及への貢献がのちに評価され、1988年には鰺ヶ沢町のはまなす公園に「山田千里・福士りつ顕彰碑」顕彰碑が建てられた。また、1990年には第41回NHK紅白歌合戦に福士りつが津軽あいや節で出場している。千里も伴奏で登場した。
津軽三味線の奏者としてより、文化的社会的な普及促進活動に生涯を賭けたのが彼の生涯だったのであろう。2004年糖尿病の悪化による合併症で死去。享年72歳だった。 ライブハウス「山唄」は、千里の没後、長男が引きついでいたが、後継者難で2016年4月に惜しまれながら閉店。「津軽三味線全国大会」は「津軽三味線世界大会」と名称を変え現在も開催されている。
【参考文献】
・松木宏泰『津軽三味線まんだら 津軽から世界へ』(邦楽ジャーナル、2011年刊)
・大條和雄『津軽三味線の誕生 民俗芸能の生成と隆盛』(新曜社、1995年刊)